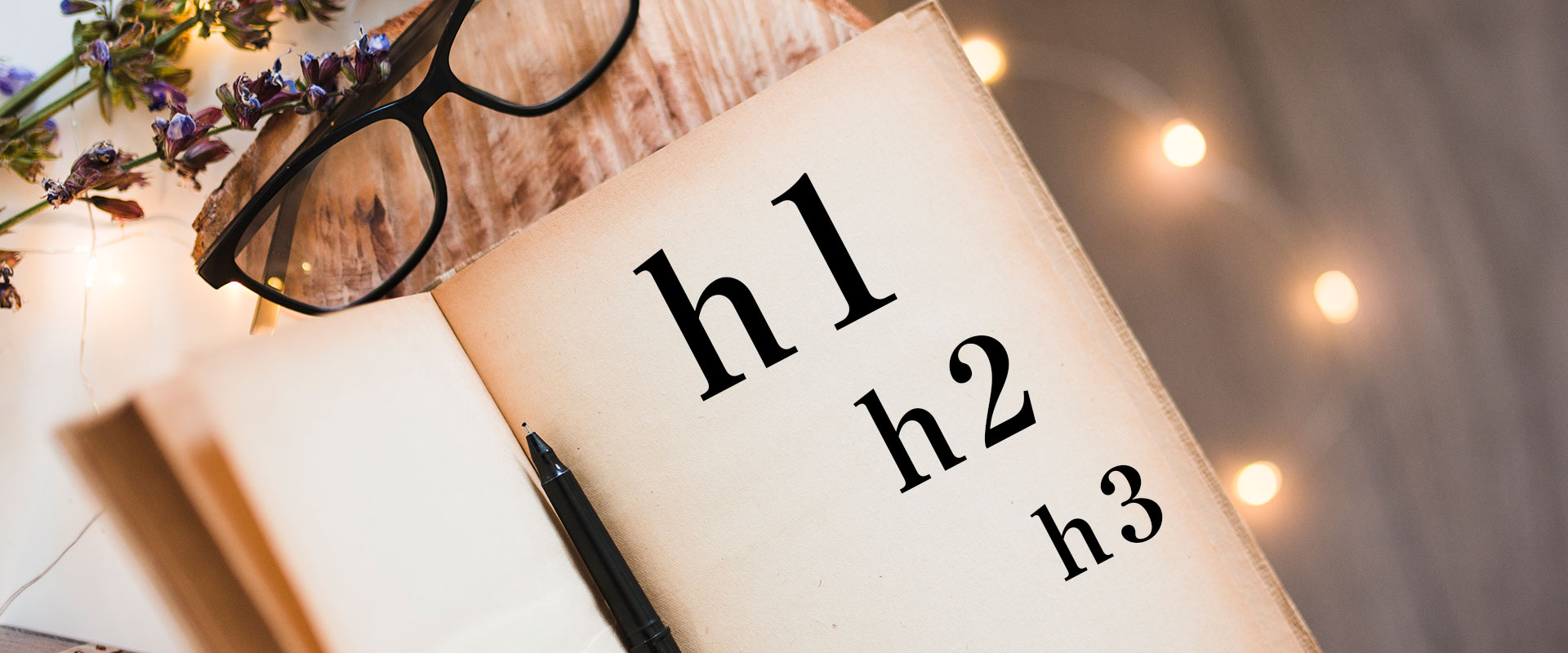【完全ガイド】見出しタグを制する者はSEOを制す!h1・h2の正しい使い方とNG例
「見出し(hタグ)って、なんとなく使っているけど本当にSEOに関係あるの?」
「h1は1つだけって聞くけど、h2やh3はどう使えばいいの?」
そんな疑問を抱えていませんか?見出しタグは、単なる文字飾りのためのものではありません。それは、ユーザーと検索エンジンへの「道しるべ」であり、あなたのコンテンツの価値を最大限に引き出すための強力なSEOの武器です。
この記事では、見出しタグの基本的な役割から、検索順位に直結する戦略的な使い方、そして多くの人がやりがちなNG例まで、網羅的に解説します。
1. なぜ見出しタグはSEOでこれほど重要なのか?
見出しタグの役割は、一言でいえば「コンテンツの骨格(アウトライン)を定義すること」です。それは、人間と検索エンジンの両方に対して、絶大な効果を発揮します。
【対ユーザー】劇的に読みやすさが向上する
長い文章が続くページを想像してみてください。どこに何が書いてあるか分からず、すぐに読む気が失せてしまいますよね。適切な見出しは、読者が内容を瞬時に把握し、興味のある部分へジャンプする手助けをします。これにより、読者の離脱率が下がり、滞在時間が延びるという、SEOにおいて非常に重要なユーザーシグナルにつながります。
【対検索エンジン】コンテンツの文脈を正確に伝える
Googleは、見出しタグを本の「目次」のように見ています。<h1>が本のタイトル、<h2>が章、<h3>が節として認識し、「このページは、〇〇というテーマについて、△△と□□の観点から解説しているんだな」と、内容の全体像と構造を正確に理解します。この理解が、あなたのページを正しく評価する第一歩となるのです。
さらに、適切に見出しを使うことで、検索結果で目立つ「強調スニペット」や「リッチリザルト」に表示されやすくなるという直接的なメリットもあります。
2. 見出しタグの基本ルール|h1からh6の正しい階層構造
見出しタグには<h1>から<h6>までの6段階があり、数字が小さいほど重要度が高くなります。これは建物の階層のようなもので、必ず守るべきルールがあります。
<h1>:大黒柱・ページの主題。 記事全体のタイトル。(原則1ページに1つ)<h2>:大見出し・章。 h1のテーマを分割する大きなセクション。<h3>:中見出し・節。 h2の内容をさらに細分化するセクション。<h4>〜<h6>:小見出し・項。さらに詳細な補足。通常はh4までで十分な場合が多い。
重要なのは、この階層を順番通りに使うことです。<h1>の次にいきなり<h3>を使ったり、<h4>の後に<h2>が出てくるような構造は、論理的におかしく、Googleを混乱させる原因になります。
3. これが正解!見出しの正しい構造サンプル
言葉で説明するよりも、実際のコード例を見るのが一番分かりやすいでしょう。以下は、理想的な見出しの構造です。
<h1>おすすめのダイエット方法10選</h1>
<p>この記事では、初心者でも始めやすいダイエット方法を10個紹介します...</p>
<h2>1. 糖質制限ダイエット</h2>
<p>糖質制限ダイエットは、食事から糖質を減らすことで...</p>
<h3>糖質制限の具体的な効果</h3>
<p>主な効果としては、体重減少や血糖値の安定が挙げられます...</p>
<h3>実践する上での注意点</h3>
<p>ただし、極端な糖質制限は健康を害するリスクも...</p>
<h2>2. 置き換えダイエット</h2>
<p>次に紹介するのは、1食を専用のドリンクやフードに置き換える...</p>
このように、<h1>を頂点として、<h2>、<h3>が親子関係のように正しく階層化されているのが分かりますね。この「骨格」をGoogleが正しく認識してくれるのです。
4. SEO効果を最大化する!見出しタグの5つの黄金ルール
基本を理解した上で、さらに一歩進んだ戦略的な使い方をマスターしましょう。
- 【ルール1】h1タグはページの主題を凝縮し、1つだけ使う
h1には、そのページで最も重要なキーワードを含め、ユーザーが「この記事には自分の知りたいことが書いてありそうだ」と一目でわかるタイトルをつけます。HTML5では複数使用も許容されていますが、SEOの観点からは今も「1ページに1つのh1」が最も安全で効果的です。 - 【ルール2】h2, h3に関連キーワードを自然に盛り込む
各セクションのテーマを表すh2やh3には、狙っているキーワードの関連語句(サジェストキーワードや共起語)を自然に含めましょう。これにより、ページのテーマ性が強化されます。
悪い例:<h2>ダイエット</h2>
良い例:<h2>運動が苦手な人でも続くダイエット方法</h2> - 【ルール3】見出しだけで内容がわかるように具体的に書く
「はじめに」「まとめ」といった抽象的な見出しは避けましょう。読者が見出しを拾い読みしただけで、記事の全体像が掴めるように、具体的で魅力的な言葉を選びます。 - 【ルール4】ユーザーの検索意図(疑問)に答える形にする
見出しを「〇〇とは?」「〇〇のやり方」「〇〇の注意点」のように、ユーザーが検索窓に入力するであろう疑問文の形にすると、検索意図にマッチしやすくなり、評価も高まります。 - 【ルール5】キーワードを詰め込みすぎない
SEOを意識するあまり、すべての見出しに同じキーワードを詰め込むのは逆効果です。不自然な文章はユーザー体験を損ない、Googleから過剰最適化(スパム)と見なされるリスクがあります。
5. やってはいけない!見出しタグのよくあるNG例
良かれと思ってやったことが、実はSEOにマイナスだったというケースは少なくありません。よくある間違いを確認しておきましょう。
- NG例1:見た目のデザインのためだけに見出しタグを使う
「文字を大きくしたいから」という理由で<h2>タグを使うのは最もよくある間違いです。デザインの調整はCSSで行い、HTMLはあくまで文章の構造を示すために使いましょう。構造とデザインは完全に分離して考えるのが鉄則です。 - NG例2:見出しタグを
<p>タグや<div>タグで囲む
見出しタグはそれ自体がブロック要素です。不要なタグで囲むと、構造が複雑になり、Googleのクローラビリティを損なう可能性があります。 - NG例3:見出しタグの中にリンク以外の装飾をしすぎる
見出しを<strong>で強調したり、色を変えるための<font>タグ(非推奨)を入れるなど、過度な装飾はコードを複雑にします。見出しはシンプルに保ちましょう。
まとめ|見出しはユーザーとGoogleへの「おもてなし」
見出しタグの最適化は、SEOの内部対策における基本でありながら、非常に奥が深い要素です。
重要なのは、見出しを単なるSEOテクニックとして捉えるのではなく、「どうすれば読者が読みやすくなるか」「どうすれば内容が伝わりやすくなるか」という、ユーザーへの「おもてなし」の心で設計することです。その結果として、Googleからの評価も自然とついてきます。
今日からあなたの記事の見出しを、もう一度見直してみませんか?その小さな改善が、サイト全体の評価を大きく引き上げる一歩になるはずです。